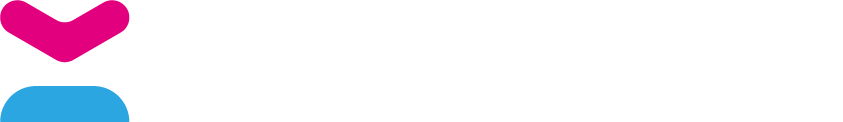Tips

【サンプル付き】RFPの書き方を徹底解説!作成する3つのメリットや作成を成功させるポイントとは?
システムの導入や開発を検討している際に、ベンダー選定で重要な役割を果たすのがRFPです。しかし、初めてRFPを作成する企業にとっては、どのような内容を記載すべきか悩むのではないでしょうか。
本記事では、RFPの書き方を具体的なサンプルとともに詳しく解説し、作成するメリットや成功のポイントについてもお伝えします。
RFPとは?目的やRFIとの違いを解説
システム導入や開発プロジェクトを成功させるためには、適切なベンダー選定が不可欠です。そのための重要なツールとなるのがRFP(提案依頼書)です。RFPは、企業がベンダーに対して具体的な提案を求める際に作成する文書で、プロジェクトの要件や条件を詳細に記載します。
適切なRFPを作成することで、複数のベンダーから同じ基準での提案を受けられるため、公正で効率的な比較検討が可能になります。また、RFPの作成プロセスを通じて、企業側も自社の課題や要望を整理できる効果があります。本セクションでは、RFPの基本的な定義や目的について詳しく解説し、混同されやすいRFIとの違いについても明確にしていきます。
これらの知識を身につけることで、より効果的なベンダー選定を実現できるでしょう。
RFPとは?
RFP(Request for Proposal)とは、「提案依頼書」を意味する文書です。企業がシステムの導入や開発を検討する際に、複数のベンダーに対して具体的な提案を求めるために作成されます。RFPには、プロジェクトの背景や目的、求める機能、予算、スケジュールなどの詳細な情報が記載されており、ベンダーはこの情報を基に最適な提案書を作成します。
RFPを通じて、企業は自社の要件に最も適したベンダーを効率的に選定できるのです。
RFPの目的
RFPを作成する主な目的は、ベンダー選定の精度を高めることにあります。詳細な要件や条件を明記することで、各ベンダーから同じ基準での提案を受けられるため、比較検討がスムーズになるでしょう。また、RFP作成のプロセスを通じて、企業側も自社の課題や要望を整理できます。さらに、後のトラブルを防ぐ効果もあります。
RFPに記載された内容は契約の基準となるため、認識の齟齬を未然に防げるのです。このように、RFPは単なる文書ではなく、プロジェクト成功の基盤となる重要なツールといえるでしょう。
RFPとRFIとの違い
RFPと混同されやすいのがRFI(Request for Information)ですが、両者には明確な違いがあります。RFIは「情報提供依頼書」と呼ばれ、ベンダーの基本的な情報収集を目的としています。例えば、どのような製品やサービスがあるのか、大まかな費用感はどの程度かといった情報を求める際に使用されるでしょう。
一方、RFPはより具体的な提案を求める文書です。プロジェクトの詳細が固まった段階で、実際の導入を前提とした提案を依頼します。つまり、RFIは情報収集段階、RFPは提案依頼段階で使用されるものです。適切なタイミングで使い分けることが、効率的なベンダー選定につながります。
RFP概要の書き方【サンプル付き】
RFPの概要部分は、プロジェクト全体の方向性を決定づける極めて重要なセクションです。この部分でベンダーがプロジェクトの本質を正しく理解できるかどうかが、その後の提案品質を大きく左右します。概要には、プロジェクトの背景、現状の課題、システム化の目的、達成したいゴール、プロジェクトのスコープなど、多岐にわたる情報を体系的に整理して記載する必要があります。
また、自社の会社情報や現行システムの構成についても詳細に記載することで、ベンダーが提案を検討する際の重要な判断材料を提供できます。さらに、表紙や目的の記載方法についても具体的なサンプルを交えながら解説していきます。
これらの要素を適切に記載することで、ベンダーから質の高い提案を引き出すことができ、プロジェクト成功への道筋を明確にできるでしょう。
表紙
表紙には、RFPのタイトル、発行日、発行者、機密情報であることの記載を含めます。例えば、「販売管理システム導入に関する提案依頼書」といった具体的なタイトルを設定し、2025年6月発行、株式会社○○システム企画部といった形で明記してください。
また、「本書は機密情報を含むため、無断転載・複製を禁止します」といった注意書きも必要です。表紙は最初に目に触れる部分のため、プロジェクトの性質が一目で分かるようなデザインにすることも大切です。シンプルながらも、企業のブランドイメージを反映させた体裁にするとよいでしょう。
| [プロジェクト名]提案依頼書(RFP) 本書は、[株式会社〇〇]が実施する[プロジェクト名]に関して、システム・サービス選定にあたって提案を依頼するための資料です。 発行日:2025年6月30日 発行者:[株式会社〇〇] ※本書は機密情報を含むため、無断転載・複製を禁止します |
本書の目的
本書の目的では、なぜこのRFPを作成したのかを明確に記載します。「弊社では、現在の販売管理業務の効率化を図るため、新たな販売管理システムの導入を検討しております。つきましては、貴社に対して最適なシステムの提案をお願いしたく、本提案依頼書を作成いたしました。」といった形で、簡潔に目的を伝えるとよいでしょう。
また、ベンダーに求める提案の内容についても触れておきます。システムの機能要件だけでなく、導入スケジュールや費用、サポート体制についても提案を求めていることを明記することで、包括的な提案を促せます。
| 現在、[株式会社〇〇]では[目的:例「営業活動の効率化」「社内業務のDX推進」など]を目的として、[対象システム・サービス]の導入を計画しています。本書(以下、RFP)は、ベンダー各社様に対し、当社の背景や要件を開示し、貴社にてご提案いただく際の指針となるものです。当社は、本書をもとに貴社のご提案を受け、本プロジェクトの委託先選定を行う予定です。 |
プロジェクトの背景
プロジェクトの背景では、なぜシステム導入が必要になったのかの経緯を説明します。例えば、「弊社は創業20年を迎え、売上規模の拡大に伴い取引先数が大幅に増加しています。しかし、現在の手作業中心の販売管理では処理能力の限界を迎えており、注文処理の遅延や在庫管理の精度低下が課題となっています。」といった具体的な状況を記載するでしょう。また、過去に検討した対策があれば、それらの結果についても触れておきます。
ベンダーがプロジェクトの必要性を理解し、適切な提案を行うために重要な情報となります。
| [現状の業務状況や課題の兆候を簡潔に記載:例「エクセルによる情報管理の限界」「属人化した業務運用」「対応ミスやクレームの増加」など]こうした状況を踏まえ、業務全体の見直しと効率化を目的に、[システム名やプロジェクト名]の導入を検討しています。 |
現状の課題
現状の課題では、解決すべき具体的な問題点を明確に記載します。「注文処理に1件あたり平均15分かかっており、1日の処理能力に限界がある」「在庫データの更新が手作業のため、リアルタイムな在庫状況の把握ができない」「売上データの集計に毎月3日を要しており、迅速な経営判断に支障をきたしている」といった定量的な課題を挙げるとよいでしょう。
また、これらの課題が業務に与える影響についても具体的に記載します。例えば、処理遅延により顧客満足度が低下している、在庫管理の不備により機会損失が発生しているといった内容です。課題を明確にすることで、ベンダーは最適なソリューションを提案できるようになります。
| [課題1]:内容[課題2]:内容[課題3]:内容[課題4]:内容(例)案件情報の共有不足により、対応の遅延やクレームが発生しているデータ管理が煩雑で、業務効率が低下している情報が一元化されておらず、意思決定に活用できない |
システム化の目的
システム化の目的では、新システム導入により達成したい目標を明記します。「注文処理時間を現在の15分から5分に短縮し、処理能力を3倍に向上させる」「リアルタイムな在庫管理により、欠品率を現在の5%から1%以下に削減する」「売上データの自動集計により、月次報告書作成時間を3日から半日に短縮する」といった具体的で測定可能な目標を設定するとよいでしょう。
また、これらの目標達成により期待される効果についても記載します。業務効率化による人件費削減、顧客満足度向上による売上増加、迅速な経営判断による競争力強化などの効果を明確にすることで、ベンダーはより効果的な提案を行えるようになります。
| [目的1](例:業務効率化)[目的2](例:情報の一元管理)[目的3](例:組織全体でのナレッジ共有)※各目的の背景や期待する効果も任意で補足してください。 |
ゴール
ゴールでは、プロジェクト完了時に達成すべき最終的な成果を明確に定義します。「2025年12月末までに新販売管理システムを本格稼働させ、全営業担当者が新システムを活用して業務を行えるようにする」「システム導入により、年間の業務効率化効果として人件費を20%削減する」といった具体的なゴールを設定するでしょう。
成功の測定基準についても記載します。システムの稼働率、処理速度、ユーザーの習熟度などの指標を明確にすることで、プロジェクトの成功を客観的に評価できるようになります。ゴールが明確であれば、ベンダーも提案内容をより具体的に検討できるはずです。
| 品質(Quality) 例:業務画面での操作(検索・保存等)が3秒以内で完了する費用(Cost) 例:総額[〇〇万円]以内での導入納期(Delivery) 例:2025年05月31日までに稼働 |
スコープ
スコープでは、プロジェクトの範囲を明確に定義し、何が含まれ何が含まれないかを記載します。「本プロジェクトには、販売管理システムの設計・開発・導入・運用開始支援が含まれます。ただし、既存データの移行作業および操作研修は別途検討とします」といった形で、明確に境界を示すとよいでしょう。また、関連する他のシステムとの連携についても触れておきます。
会計システムや在庫管理システムとの連携が必要な場合は、その詳細についても記載することが重要です。スコープが曖昧だと、後に追加費用が発生したり、期待していた機能が含まれていなかったりするトラブルにつながりかねません。
| [対象業務や機能:例「営業支援システムの構築・運用」][導入支援の範囲:例「教育・マニュアル整備」「運用保守体制の構築」][その他:IT機器購入やネットワーク設定の有無など] |
会社情報
会社情報では、自社の基本的な情報を記載し、ベンダーが提案を検討する際の参考情報とします。「社名:株式会社○○、設立:2003年、資本金:5,000万円、従業員数:150名、事業内容:製造業、年商:50億円」といった基本情報に加え、組織構成や事業の特徴についても記載するとよいでしょう。また、IT環境についても触れておきます。
現在使用しているシステムの概要、社内のIT人材の状況、情報セキュリティに関する方針などの情報は、ベンダーが適切な提案を行うために必要な情報です。これらの情報により、ベンダーは企業規模や業界特性に適した提案を検討できるようになります。
| 会社名:[例:株式会社〇〇]設立年月:[例:2020年04月]所在地:[例:東京都〇〇区〇〇]代表者:[氏名・役職]事業内容:[簡単な業種説明]従業員数:[例:100名]資本金:[例:1億円]年商:[例:10億円]組織図(必要に応じて記載・添付) |
現行のシステム構成
現行のシステム構成では、既存のIT環境について詳細に記載します。「現在はExcelベースでの販売管理を行っており、各営業担当者が個別にファイルを管理している状況です。会計システムは○○社の△△を使用しており、月末に手作業でデータを入力しています」といった具体的な現状を記載するでしょう。
また、使用しているハードウェアやネットワーク環境についても記載します。サーバーの仕様、端末の台数、ネットワークの構成などの技術的な情報は、新システムの設計において重要な要素となります。現行システムの課題や制約についても明記することで、ベンダーはより適切なシステム構成を提案できるようになるでしょう。
| 現状の業務を支えているシステムやツールを簡単に説明] (例:商品管理と売上は自社サーバで管理、顧客情報はクラウド上のサービス、営業情報はエクセルベースに)※可能であればシステム構成図やデータフロー図を添付するとわかりやすくなります。 |
機器情報
機器情報では、現在使用している機器の詳細な仕様を記載します。「サーバー:Windows Server 2019、CPU:Intel Xeon、メモリ:32GB、ストレージ:SSD 1TB」「クライアント端末:Windows 11搭載PC 30台、タブレット端末 10台」といった具体的な仕様を明記するとよいでしょう。また、これらの機器の導入時期や更新予定についても記載します。
古い機器については更新を検討していることを伝えることで、ベンダーは最新の技術を活用した提案を行えるようになります。ネットワーク機器やセキュリティ機器についても同様に記載し、新システムとの互換性や連携について検討材料を提供することが重要です。
| サーバ:[台数・OS・型番など]クライアントPC:[台数・OS・機種など]モバイル端末等:[台数・種類・スペック] |
RFP提案依頼内容の書き方【サンプル付き】
提案依頼内容は、ベンダーに具体的に何を求めるかを明確に示すRFPの核心部分です。ここで詳細かつ具体的な要求事項を記載することで、各ベンダーから比較検討しやすい質の高い提案を得られるでしょう。
本セクションでは、受注側の会社情報から契約内容まで、各項目の効果的な書き方を具体的なサンプルとともに詳しく解説していきます。
受注側の会社情報
受注側の会社情報では、提案を行うベンダーに求める基本的な情報を明記します。
「会社概要(設立年、資本金、従業員数、事業内容)」「類似プロジェクトの実績(過去3年間の導入事例、業界別の実績)」「保有する技術者の資格や経験」「財務状況(直近3年間の売上高、営業利益)」といった情報の提出を求めるとよいでしょう。また、提案チームの体制についても詳細を求めます。プロジェクトマネージャーの経験年数、システムエンジニアの技術力、サポート要員の配置予定などの情報により、ベンダーの実行能力を評価できます。
これらの情報は、技術力だけでなく、プロジェクトを最後まで遂行できる体制があるかを判断する重要な要素となるでしょう。
| 本提案に関わる全ての法人・団体名を記載してください。 再委託先が存在する場合は、その企業名・役割・責任範囲も明確にしてください。※RFIを実施済みの場合は本項目の記載を省略可能です。RFPのみで選定を行う場合は、貴社の業種・実績・強みがわかる資料の添付もお願いいたします。 |
提案システム概要・構成
提案システム概要・構成では、ベンダーに求めるシステムの全体像を記載します。「Webベースの販売管理システムで、受注・出荷・請求・売上管理の一連の業務をカバーすること」「同時接続ユーザー数50名以上に対応すること」「レスポンス時間は3秒以内を維持すること」といった基本的な要件を明記するとよいでしょう。
また、システム構成についての要求も記載します。クラウド型かオンプレミス型かの選択、データベースの種類、開発言語の指定などの技術的な要件も含めることが重要です。セキュリティ要件についても詳細に記載し、個人情報保護や機密情報の取り扱いに関する要求を明確にすることで、安全性の高いシステムの提案を促せるでしょう。
| 【概要】以下の情報をご提示ください。提案対象システムの主要機能一覧操作画面の構成イメージ今後予定されている機能追加の有無と概要当社の要件との適合性、及び競合他社との比較優位性【構成】 システムに必要なハードウェアスペックネットワーク構成図、およびインフラ構成オンプレミス/クラウドの別、および提供方式 |
機能要件
機能要件では、システムに必要な具体的な機能を詳細に記載します。「受注管理:顧客からの注文登録、注文内容の変更・キャンセル、注文状況の確認」「在庫管理:リアルタイムな在庫数量の把握、安全在庫の設定、発注点管理」「売上分析:月次・四半期・年次の売上レポート、商品別・顧客別の売上分析」といった具体的な機能を列挙するとよいでしょう。また、各機能の詳細な仕様についても記載します。
画面の操作性、帳票の出力形式、他システムとの連携方法などの詳細を明記することで、ベンダーは具体的な開発内容を検討できるようになります。必須機能と希望機能を区別して記載することも重要です。これにより、予算に応じた段階的な導入も検討できるでしょう。
| 以下の機能を含むソリューション提案を求めます。詳細は別紙にて記載しますが、以下の要件を満たす機能概要を記載してください。例:営業支援システムにおける主な要件 案件の進捗・担当者・金額などを一元管理できる機能タスクのテンプレート化と通知機能売上予測の可視化とレポート作成機能モバイル環境からの入力・閲覧機能 |
プロジェクトのスケジュール
プロジェクトのスケジュールでは、希望する導入スケジュールを明確に記載します。「2025年7月:ベンダー選定完了」「2025年8月:要件定義開始」「2025年10月:設計・開発開始」「2025年12月:テスト・導入完了」といった具体的なマイルストーンを設定するとよいでしょう。また、各フェーズで必要な期間や重要な制約条件についても記載します。
例えば、年末年始の繁忙期は避けたい、決算期までに稼働させたいといった制約があれば明記することが重要です。ベンダーには、このスケジュールに対する実現可能性の評価と、より効率的なスケジュール案があれば提案することを求めるとよいでしょう。
| 週/月単位でのプロジェクト全体スケジュールをご提出ください。各フェーズでの担当(自社/弊社/外注先等)を明示し、役割分担が明確になるようご配慮ください。 |
プロジェクトの体制図
プロジェクトの体制図では、発注者側とベンダー側の役割分担と体制を明確にします。「発注者側:プロジェクトオーナー(役員レベル)、プロジェクトマネージャー、業務担当者(各部門から1名ずつ)、システム管理者」「ベンダー側:プロジェクトマネージャー、システムエンジニア、プログラマー、テスト担当者」といった体制を想定していることを記載するとよいでしょう。
また、意思決定プロセスや報告体制についても明記します。週次の進捗報告、月次のステアリングコミッティの開催、重要な判断が必要な際のエスカレーション手順などを定めることで、プロジェクトの円滑な推進を図れるでしょう。
ベンダーには、この体制に対する意見や改善提案も求めることが重要です。
| プロジェクト参画予定メンバーの氏名(未定の場合は「調整中」)各メンバーの役割・担当領域プロジェクトマネージャーの経歴資料の添付※PMの実績と適性は重視しています。過去の類似プロジェクトの経験等を記載してください。 |
成果物
成果物では、プロジェクト完了時に納品を求める具体的な成果物を明記します。「システム一式(ソースコード、実行ファイル、データベース構成)」「設計書(要件定義書、基本設計書、詳細設計書)」「テスト仕様書・結果報告書」「ユーザーマニュアル・運用マニュアル」といった成果物を列挙するとよいでしょう。
また、各成果物の品質基準についても記載します。ドキュメントの記載レベル、ソースコードのコメント率、テストカバレッジの目標値などの品質基準を明確にすることで、一定の品質を確保できます。成果物の納品形式(紙媒体、電子ファイル)や更新時の対応についても明記することが重要でしょう。
| 本プロジェクトにおいて納品予定の成果物をリスト化してください。また、可能であれば類似プロジェクトで作成された成果物の一部サンプルをご提示ください。 |
サポート体制
サポート体制では、システム稼働後の保守・運用支援について要求事項を記載します。「平日9時〜18時のヘルプデスク対応」「緊急時(システム停止等)の24時間対応」「月次の定期メンテナンス」「年次のシステムバックアップとリストア確認」といった具体的なサポート内容を求めるとよいでしょう。また、サポートのレベルについても明記します。
問い合わせへの回答時間(2時間以内の初回回答)、障害復旧時間の目標値(4時間以内の復旧)、定期訪問の頻度(月1回)などの具体的な基準を設定することが重要です。サポート費用の考え方についても確認し、月額固定か従量課金かなどの料金体系についても提案を求めるとよいでしょう。
| 以下の情報をご記載ください。運用開始後の問い合わせ窓口の情報(受付時間・連絡手段・対応フロー)障害発生時の対応プロセスと体制SLA(サービスレベル合意)の有無と内容 |
概算費用
概算費用では、プロジェクト全体にかかる費用の内訳と総額を求めます。「初期費用:システム開発費、導入支援費、教育研修費」「月額費用:ライセンス費、保守費、クラウド利用料」「その他費用:追加カスタマイズ費、データ移行費」といった費用項目別の概算を求めるとよいでしょう。また、費用の根拠についても説明を求めます。
工数の算出方法、人月単価の設定、外部調達費の内容などの詳細を明記してもらうことで、費用の妥当性を評価できるようになります。複数のプランやオプションがある場合は、それぞれの費用比較も求めることが重要です。予算制約がある場合は、その範囲内での最適な提案も併せて求めるとよいでしょう。
| 初期費用・月額費用をそれぞれ下記のように明示してください。初期費用:開発費・インフラ費・教育費などの内訳と総額月額費用:保守・ネットワーク・運用費の内訳と単価※合計金額のみの提示ではなく、詳細な内訳を明示してください。 |
制約事項
制約事項では、プロジェクト実施において考慮すべき制約条件を明記します。「既存システムとの並行稼働期間は最小限にすること」「営業時間中のシステム停止は月1回2時間以内とすること」「個人情報保護法への完全準拠」「社内セキュリティポリシーの遵守」といった制約を記載するとよいでしょう。
また、技術的な制約についても明記します。使用できないソフトウェアやツール、ネットワークの帯域制限、データセンターへのアクセス制限などの制約があれば、事前に伝えることが重要です。これらの制約条件を踏まえた提案を求めることで、実現可能性の高いシステムの提案を得られるでしょう。
制約条件によって追加コストが発生する場合は、その影響についても評価してもらうことが大切です。
| 本プロジェクトに関して、現在判明している制限事項(例:同時アクセス数制限、拡張不可領域など)がある場合は、必ずご提示ください。 |
契約内容
契約内容では、想定している契約条件について記載します。「契約形態:請負契約または準委任契約」「支払条件:着手金30%、中間金40%、完成金30%」「瑕疵担保期間:システム稼働後1年間」「機密保持義務:プロジェクト期間中および終了後3年間」といった基本的な契約条件を明記するとよいでしょう。また、知的財産権の取り扱いについても明確にします。
開発されたシステムの著作権、カスタマイズ部分の権利、第三者ライブラリの使用に関する権利処理などの内容を明記することが重要です。契約解除条件や損害賠償の範囲についても記載し、万が一の場合に備えた条件を明確にしておくことで、双方にとってリスクの少ない契約を締結できるでしょう。
| 契約形態(準委任/請負など)支払スケジュール(成果物ベース/月額など)分割払いや条件付き支払いがある場合は明示してください |
RFP選考の進め方の書き方【サンプル付き】
選考プロセスの透明性と公平性を確保するためには、選考の進め方を事前に明確に示すことが重要です。ベンダーにとって選考プロセスが明確であることは、提案書作成の指針となり、より適切な提案を促すことにつながります。
本セクションでは、これらの選考プロセスについて具体的なサンプルを交えながら、効果的な記載方法を詳しく解説していきます。
選考スケジュール
選考スケジュールでは、RFP発行から契約締結までの詳細なスケジュールを記載します。「6月10日:RFP発行・ベンダーへの配布」「6月17日:質問受付締切(書面にて受付)」「6月20日:質問回答の配布」「7月5日:提案書提出締切(午後5時必着)」「7月10日〜12日:プレゼンテーション実施」「7月15日:ベンダー選定結果通知」「7月末:契約締結」といった具体的な日程を設定するとよいでしょう。
また、各段階での留意事項についても記載します。質問は書面のみ受け付ける、プレゼンテーション時間は1社あたり60分、結果通知は選定されたベンダーから順次行うといった運用ルールを明確にすることで、スムーズな選考プロセスを実現できるでしょう。
| 選考は、以下のスケジュールに基づいて進行する予定です。各日程においてご都合がつかない場合は、事前にご相談ください。2025年09月30日(水):提案書提出締切2025年10月1日(水)~ 10月5日(日):提案内容の 書類選考2025年10月8日(水)~ 10月15日(日):提案に関するプレゼン実施2025年10月15日(水)~ 10月22日(日):社内での選定・合意形成2025年10月23日(水)~ 10月31日(金):委託先決定及び契約手続き2025年11月01日(日):プロジェクト開始予定日※スケジュールは調整の可能性があります。 |
提案書提出先
提案書提出先では、提案書の提出方法と提出先を詳細に記載します。「提出先:株式会社○○ システム企画部 RFP担当者宛」「住所:〒100-0001 東京都千代田区○○1-2-3 ○○ビル5階」「電話:03-1234-5678」「メールアドレス:rfp@company.co.jp」といった連絡先情報を明記するとよいでしょう。
また、提出方法についても具体的に記載します。郵送の場合は書留郵便を指定する、電子ファイルの場合はファイル形式とサイズ制限を明記する、CD-ROMでの提出も可能とするといった選択肢を提示することが重要です。提案書の部数(正本1部、副本3部)や梱包方法についても指定し、確実な提出を促すとよいでしょう。
| 提案書は以下の宛先へ電子ファイル形式(PDF推奨)でご提出ください。提出先企業名:株式会社〇〇担当部署・担当者名:〇〇部 〇〇 〇〇メールアドレス:xxxx@xxxx.co.jp提出期限:2025年04月30日(水)17:00まで※期限を過ぎた場合は、選考対象外とさせていただくことがあります。 |
評価基準
評価基準では、提案書を評価する具体的な基準と配点を明記します。「技術力:30点(提案システムの技術的優位性、実現可能性)」「コスト:25点(初期費用・運用費用の妥当性、コストパフォーマンス)」「実績:20点(類似案件の実績、顧客満足度)」「提案内容:15点(要件への適合度、提案の独自性)」「サポート体制:10点(保守・運用サポートの充実度)」といった評価項目と配点を設定するとよいでしょう。
また、各評価項目の詳細な評価ポイントについても記載します。技術力では最新技術の活用度や拡張性を重視する、コストでは総所有コスト(TCO)を重視するといった評価の観点を明確にすることで、ベンダーは評価基準に沿った提案を行えるようになります。
| ご提出いただいた提案は、以下の観点から総合的に評価いたします。1.ソリューション評価要件への適合性(本RFPに記載のすべての要件を満たすこと)拡張性・柔軟性(機能追加・変更の容易さ)セキュリティおよび可用性(信頼性・保全性・障害時の対応力)ユーザーサポート(マニュアル、ヘルプデスク等の整備)2.マネジメント評価プロジェクト体制の明確性(PMの経験・スキル、メンバー構成)タスク・責任範囲の明示スケジュール管理と進行管理能力3.価格評価初期費用とランニングコストの妥当性各費用の内訳と算出根拠の明確性4.ベンダー評価組織の安定性と事業継続性類似プロジェクトの実績と経験自社業界への理解度※上記評価項目を基に、選定委員会にて総合判断の上、発注先を決定いたします。 |
RFPを作成する3つのメリット
RFPを作成することで得られるメリットは、単なる文書作成以上の価値があります。適切なRFPがあることで、プロジェクト成功の確率を大幅に向上させることができます。詳細な要件定義により、ベンダーとの認識齟齬を防ぎ、自社の真の課題を明確化できるため、最適なシステム選定が実現できます。
これらのメリットを最大限に活用することで、効率的なベンダー選定とプロジェクトの成功につなげられます。
①ベンダーに自社の要望を漏れなく伝えられる
RFPを作成する最大のメリットの一つは、自社の要望をベンダーに正確かつ詳細に伝えられることです。口頭での説明では伝わりにくい細かな要求事項も、文書化することで確実に共有できるでしょう。
例えば、業務フローの詳細、画面レイアウトの希望、帳票の出力形式、他システムとの連携仕様などの具体的な要求を明記できます。また、優先順位も明確に示せるため、ベンダーは重要な機能から順に検討を進められるようになります。さらに、RFPがあることで、提案書作成時や契約時に「言った・言わない」といった認識の齟齬を防げます。
これにより、プロジェクト開始後のトラブルを大幅に減らすことができ、円滑なプロジェクト推進が可能になるのです。
②自社の課題や目的を明確にできる
RFP作成のプロセスを通じて、自社の課題や目的を改めて整理できる効果があります。普段の業務では漠然と感じていた問題点も、RFPに記載するために具体化する過程で、真の課題が明らかになるでしょう。例えば、「業務が非効率」という曖昧な問題意識が、「注文処理に1件15分かかり、1日20件が限界」という具体的な課題として明確になります。
また、関係部署との議論を重ねることで、各部門が抱える異なる課題も浮き彫りになります。営業部門は顧客情報の一元管理を求め、経理部門は売上データの自動集計を重視するといった具合に、多角的な視点で課題を捉えられるようになるのです。
このように課題を明確化することで、システム導入の真の目的が見えてくるため、より効果的なシステム選定が可能になります。
③ベンダーからの提案の比較がスムーズにできる
RFPがあることで、複数のベンダーから同じ基準での提案を受けられるため、公正で効率的な比較検討が可能になります。各社が同じ要件に対して提案するため、機能面、コスト面、技術面での違いが明確に見えるでしょう。例えば、A社は機能の豊富さに優れ、B社はコストパフォーマンスが高く、C社は導入実績が豊富といった具合に、各社の特徴を客観的に評価できます。
また、提案書の構成も統一されるため、評価作業の効率化も図れます。評価チームのメンバーが同じ項目について検討できるため、評価のばらつきを抑制できるのです。さらに、定量的な評価基準を設けることで、感情的な判断を排除し、論理的なベンダー選定を行えるようになります。
これにより、後になって「なぜこのベンダーを選んだのか」という疑問が生じることを防げるでしょう。
RFP作成を成功させる3つのポイント
質の高いRFPを作成するためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。プロジェクト目的の明確化、関係者からの幅広い意見収集、専門家への相談などの要素が成功の鍵となります。事前準備を行っておくことで、実用性の高いシステム導入が可能になります。
これらのポイントを意識することで、ベンダーから質の高い提案を引き出し、プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができます。
①プロジェクトの目的を明確にする
RFP作成において最も重要なのは、プロジェクトの目的を明確に定義することです。「なぜシステムを導入するのか」「どのような効果を期待するのか」「成功をどう測定するのか」といった根本的な問いに対する答えを明確にしておく必要があります。目的が曖昧だと、ベンダーから的外れな提案を受けることになりかねません。
例えば、「業務効率化」という漠然とした目的ではなく、「注文処理時間を50%短縮し、年間人件費を1,000万円削減する」といった具体的で測定可能な目的を設定するとよいでしょう。また、短期的な目的だけでなく、中長期的なビジョンも明確にすることが重要です。
将来的な事業拡大や新サービス展開を見据えた拡張性の要求なども含めることで、長く使えるシステムの提案を得られるようになります。
②経営層やユーザー部門など様々な人から意見を聞く
RFPの作成は、システム部門だけで行うのではなく、経営層から現場のユーザーまで幅広い関係者の意見を取り入れることが重要です。経営層からは事業戦略との整合性や投資対効果の観点での意見を、現場のユーザーからは実際の業務フローや使い勝手に関する要望を聞くとよいでしょう。
例えば、営業部門からは顧客管理機能の充実を、経理部門からは請求書発行の自動化を、管理部門からは権限管理の強化をといった具合に、部門ごとに異なる要求を整理できます。
また、IT部門からは技術的な制約やセキュリティ要件についての意見も重要です。これらの多様な意見を調整し、優先順位を付けてRFPに反映させることで、全社的に受け入れられるシステムの導入が可能になります。
意見収集の際は、ワークショップやヒアリングなどの手法を活用するとよいでしょう。
③RFP作成の際は専門家に相談する
RFPの品質を高めるためには、システム導入の専門家やコンサルタントに相談することを強く推奨します。専門家は多くのプロジェクトを経験しているため、見落としがちな要件や注意すべきポイントを指摘してくれます。また、最新の技術動向や業界のベストプラクティスについても助言を得られます。
例えば、クラウド化の進展により従来のオンプレミス型システムよりもSaaS型の方が適している場合があることや、AI技術の活用により業務の自動化が可能になることなどの情報を提供してくれるかもしれません。さらに、RFPの文書構成や記載内容についても専門的な観点からアドバイスを受けられます。
株式会社KIYOLACAでは、豊富なシステム導入実績を活かしたRFP作成支援を提供しています。
技術的な専門用語の使い方、評価基準の設定方法、契約条件の記載方法などについて、当社の経験豊富な専門家がより完成度の高いRFP作成をサポートしています。
RFP作成は株式会社KIYOLACAへ
本記事では、RFPの基本的な概念から具体的な書き方、作成時のポイントまでを詳しく解説してきました。適切なRFPがあることで、ベンダー選定の精度が向上し、プロジェクトの成功確率を大幅に高められるでしょう。
株式会社KIYOLACAでは、豊富な経験と専門知識を活かして、お客様のRFP作成を全面的にサポートいたします。当社のコンサルタントは、様々な業界でのシステム導入プロジェクトに携わっており、お客様の業務特性や課題に応じた最適なRFPの作成をお手伝いできます。
また、RFP作成だけでなく、ベンダー選定から導入支援まで、プロジェクト全体を通してサポートすることも可能です。システム導入でお悩みの際は、ぜひ株式会社KIYOLACAにご相談ください。経験豊富な専門家が、お客様のプロジェクト成功に向けて最適なソリューションをご提案いたします。
KIYOLACAへのご相談はこちらから