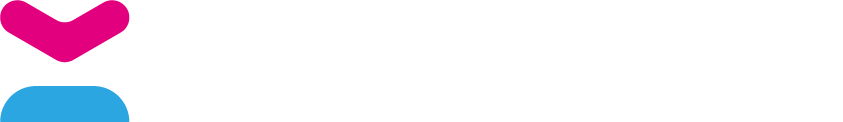Tips

RFPと要件定義書・RFI・RFQの違いとは?RFPを作成するメリットや成功させる9つのポイントを解説
システムの導入や開発を外部のベンダーに依頼する際、「RFP」「要件定義書」「RFI」「RFQ」などの専門用語に戸惑った経験はありませんか?これらの言葉はどれも提案依頼や開発に関わる重要な文書ですが、意味や役割はそれぞれ異なります。特に「RFP(提案依頼書)」と「要件定義書」の違いは混同されがちです。
この記事では、それぞれの文書の違いや役割をわかりやすく解説するとともに、RFPを作成するメリットや注意点、成功のコツまで詳しく紹介します。初めてシステム開発を検討する企業も、この記事を読めば、失敗を防ぎ、最適なベンダー選びに役立てられるようになるでしょう。
RFPとは?

RFPは「Request for Proposal」の略で、日本語では「提案依頼書」と呼ばれています。これは、システム開発や業務委託などを外部のベンダーに依頼する際に、発注側の企業が「こういう提案をしてください」と自分たちの要望や期待をまとめて伝えるための大切な文書です。
RFPには、発注者がどんな目的や課題を抱えているのか、どのような機能やサービスを望んでいるのか、納期や予算の目安など、プロジェクトに必要な情報がしっかりと記載されます。ベンダーはこのRFPをもとに、自社ならではのアイデアや解決策を盛り込んだ提案書を作成します。
つまり、RFPは単なる見積もりの依頼ではなく、「こんな悩みを解決したいので、御社の知恵や経験を活かした提案をお願いします」という、前向きなコミュニケーションのきっかけになるものです。システム開発をスムーズに進めるためには、最初の段階でベンダーとしっかり認識を合わせることがとても大切です。そのため、RFPはプロジェクトの成功を左右する重要な役割を担っていると言えるでしょう。
RFPの目的と作成者

RFPは、外部ベンダーに発注する際に、計画のズレや認識の違いを防ぐために欠かせない役割を果たすということが分かりました。そのため、RFPを作成する際には、自社の現状や課題、そして本当に必要としていることをしっかり把握し、整理することがとても重要と言えます。
正確なRFPを作成するために、「PFPが何のために行われるのか」や「RFPは誰がどのようにして作っていくのか」ということも確認しておきましょう。
RFPの目的
RFPの最大の目的は、発注者が自社の課題や希望をしっかりと整理し、それをベンダーに正確に伝えることで、最も自社のニーズに合った提案を引き出すことにあります。RFPがしっかりしていれば、ベンダーは発注者の目的や制約条件、求める成果を正確に理解できるため、自社の強みや経験を活かした具体的な提案を返しやすくなります。
また、複数のベンダーから提案を受ける場合でも、RFPの内容が明確であれば、各社の提案を公平に比較しやすくなります。これにより、費用対効果に優れた選択や後々のトラブルを防げる可能性が高まります。
RFPは、単なる依頼書ではなく、発注側が自社の課題や要望を明確に整理し、ベンダーとの認識のズレを防ぐための「計画書」とも言える存在です。しっかりとしたRFPを作成することで、プロジェクト全体の方向性が定まり、スムーズで納得感のあるシステム開発が実現しやすくなるでしょう。
RFPの作成者
RFPの作成は、基本的にシステムを導入したいと考えている会社側で行います。具体的には、そのシステムを実際に使う部署や、情報システム部門、またはプロジェクトマネージャーが中心となって、必要な情報を整理しながらRFPをまとめていきます。
ただし、自社に十分なノウハウがない場合や、プロジェクトの規模が大きく複雑な場合には、コンサルタントや外部の専門家の力を借りることも珍しくありません。特に、要件の整理やRFPの構成、ベンダーを選ぶための評価基準づくりなどは、第三者の客観的な視点が加わることで、より分かりやすく、納得感のある内容に仕上がりやすくなります。
「自分たちだけでは難しいかも」と感じたときは、無理をせず外部のサポートを活用するのもひとつの方法です。そうすることで、RFPの質が高まり、より自社に合ったベンダーと出会える可能性も広がります。
RFPと要件定義書・RFI・RFQの違い
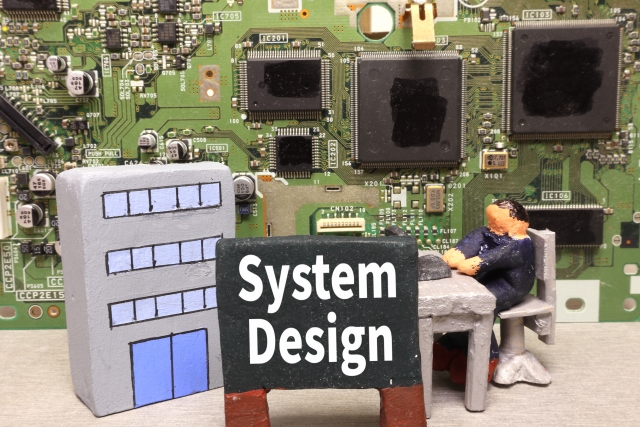
RFPはシステム導入や開発の発注において重要な役割がありますが、似たような書類として「要件定義書」「RFI」「RFQ」などがあります。これらは目的や作成されるタイミングが異なるため、混同してしまうとプロジェクトがうまく進まない原因になるかもしれません。
ここで、RFPと要件定義やその他の文書の違いを丁寧に解説していきますので、それぞれの文書の役割の明確な理解に役立ててください。
RFPと要件定義書の違い
RFPと要件定義書は、どちらもシステム開発プロジェクトの計画段階で欠かせない文書ですが、その役割や内容には大きな違いがあるため、それぞれの役割を理解して、適切に使い分けることが大切です。
まずRFP(提案依頼書)は、「こんなシステムを作りたい」「こういう課題を解決したい」といった発注者側の目的や要望、現状の課題などをまとめ、ベンダーに対して「どんな提案ができるか教えてください」と依頼するための文書です。RFPの段階では、まだ具体的な仕様や機能の細部までは決まっていません。そのため、RFPは発注者の理想や希望を幅広く伝え、ベンダーから多様な提案を引き出すための“はじめの一歩”といえるでしょう。
一方、要件定義書は、RFPで選ばれたベンダーと一緒に「どのようなシステムを、どんな仕様・機能で作るか」を具体的に決めていくための文書です。ここでは、「顧客管理を効率化したい」という抽象的な要望から一歩進んで、「顧客情報の登録や検索、編集機能」「履歴管理」「アクセス権限の設定」など、実際に必要な機能や条件が細かく記載されます。つまり、要件定義書はシステム設計や開発の土台となる、実務的で詳細な計画書です。
このように、RFPは「こんなことを実現したい」という発注者の想いを形にするためのスタート地点、要件定義書は「その想いをどうやって実現するか」を具体化するための設計図、と考えると分かりやすいでしょう。
RFPとRFIの違い
RFI(情報提供依頼書)は、RFPと同様に発注者側が作成してベンダーに提出する書類ですが、使用目的やタイミングが異なります。
RFIはRFPの前段階の、まだ自社の課題やニーズが明確でない初期段階で、業界の最新動向や技術の種類、各ベンダーがどのようなサービスを提供できるのかといった幅広い情報(どんな技術があるのか、似た課題はどう解決されているか、予算や期間はどの程度かなど)を集めるために使われます。発注者側は、このRFIでベンダーから概略的な情報をもとに自社の方針や要望を整理し、課題やニーズが明確になった段階でRFPを作成していくことになります。
RFIは「情報収集のための質問状」で具体的な提案をベンダーに依頼するためのRFPをサポートするために必要な文章と言えるでしょう。
RFPとRFQの違い
RFQ(Request for Quotation/見積依頼書)も、RFPと同様に発注者側が作成してベンダーに提出する書類ですが、使用されるタイミングや目的が異なります。
RFQは、すでにシステムの仕様や要件が明確に決まっている段階で、「この内容でどのくらいの費用がかかるのか」「納期はいつになるのか」といった具体的な見積もりを複数のベンダーから取得するために使われる書類です。そのため、RFQは提案の幅や創意工夫を求めるものではなく、あくまで条件が明確なもとでのコストや納期の比較が中心となります。パッケージソフトや既製品の購入、あるいは仕様が固まった開発案件で利用されることが多いです。
一方で、RFPは発注者の課題や要望に対してベンダーの提案力や技術力を引き出し、より良い解決策を募るための文書です。まだ実現方法が定まっていない場合や、技術的な提案を期待する段階でRFPが活用されます。
つまり、RFPは「提案依頼」、RFQは「価格見積もり依頼」として、システム導入の各段階で使い分けることが重要です。適切なタイミングでこれらの文書を発行することが、スムーズなプロジェクト推進のポイントとなります。
RFPを作成する7つのメリット
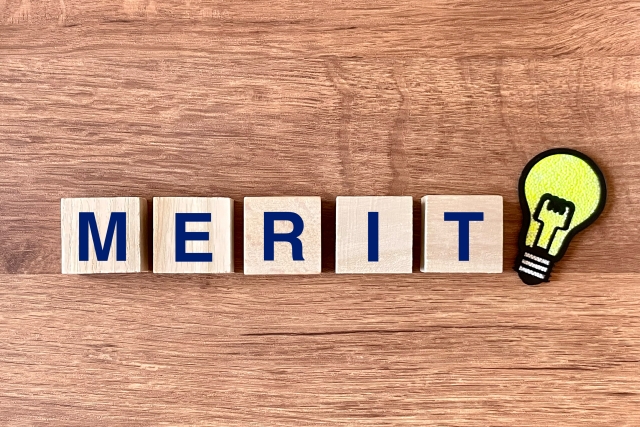
ここまで、RFPがどのようなものなのかということについて詳しく解説してきました。RFPはただの書類作成と考えられてしまうことがありますが、上記からシステム導入や開発を成功させるために非常に重要なツールだといえます。
その重要性は、RFPをしっかり作成することで得られるメリットからもうかがい知れます。ここでメリットを大きく7つに分け、そのメリットが得られる理由をご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
①自社の要望をベンダーに抜け漏れなく適切に伝えられる
RFPを作成するメリットの1つめは、自社の要望をベンダーに抜け漏れなく適切に伝えられることです。
RFPの作成過程で、自社のニーズや課題、求める成果を整理・体系化することで、単なる「こんなシステムがほしい」という漠然としたイメージではなく、具体的でわかりやすい要望をまとめることができます。伝えたいポイントが明確になっていれば、ベンダー側も誤解なく理解できるため、最適な提案が集まりやすくなるでしょう。
反対に、要望が曖昧なまま発注してしまうと、開発が始まってから「思っていたのと違う」といったミスマッチが起きやすく、追加工数やトラブルの原因になってしまうことがあります。RFPはベンダーとのコミュニケーションを円滑にし、スムーズな提案依頼を実現するためにとても重要なのです。
②自社の現状や課題を明確にできる
RFPの作成で得られるメリットの2つめは、RFPを作成することで自社の現状や課題を明確にできる点です。
RFPの作成過程では、自社の業務フローや現行システムの問題点を丁寧に整理する必要があり、これによって普段は漠然と感じていた業務の非効率や課題が、具体的な言葉として浮かび上がります。例えば、手作業によるデータ入力の多さや情報共有の遅れといった問題も、書き出すことで社内で共有しやすくなります。課題を正確に把握できれば、システムに求める改善点や優先順位も自然と明確になり、さらにこの整理作業が社内の関係者との意見交換を促すきっかけにもなります。
こうしたプロセスを通じて、RFP作成は単なる外部依頼の準備にとどまらず、自社の業務改善の土台づくりとしても大きな意味を持つことになるでしょう。
③自社に合った最適なベンダーを見極めやすくなる
RFPを詳細かつ具体的に作成することで、自社に最適なベンダーを見極めやすくなる点もメリットとして挙げられます。
RFPがしっかりしていれば、各ベンダーは自社のニーズに合わせた的確な提案を出しやすくなり、単に価格が安いだけの業者ではなく、自社の課題や目的に合ったパートナーを選びやすくなります。また、ベンダーごとの技術力や提案内容、対応力なども比較しやすくなり、同じ条件のもとで提案の質や内容を明確に評価できるようになるでしょう。
その結果、費用だけでなく品質やサポート体制も含めて総合的に判断でき、長期的に良好な関係を築けるベンダー選定につながる可能性が高まり、プロジェクト成功率の向上が期待できます。
④開発スケジュールや納期に無理がないか確認できる
開発スケジュールや納期に無理がないか確認できる点もRFPの大きなメリットです。
RFPにはプロジェクトのスケジュールや納期の希望を明記することが多いため、ベンダーは自社のリソースや技術力を踏まえた現実的なスケジュール案を提案できます。発注者側も複数の提案内容を比較することで、無理のないスケジュールかどうかを客観的に判断できる材料が得られます。この段階で納期に無理があれば事前に調整できるため、後々のトラブルや納期遅延のリスクを減らすことができるでしょう。
また、適切なスケジュール感を関係者間で共有できるため、社内の準備や調整もスムーズに進めやすくなる効果にも期待ができます。
⑤トラブル発生を抑制できる
メリットの5つめは、トラブル発生を抑制できることです。
RFPを通じて要望や条件を明確にしておくことで、後々の認識違いや誤解を防ぐ大きな効果があります。曖昧な依頼や口頭だけの説明では、ベンダーとの間で「言った」「言わない」といったトラブルが起こりやすくなりますが、RFPにしっかりと書面で記録しておけば、双方の合意事項として扱うことができ、万が一問題が起きた際の重要な証拠にもなります。
さらに、リスク管理やトラブル対策の項目をRFPに含めておくことで、事前に防止策を講じやすくなるのも大きなメリットです。このように、RFPはプロジェクトの透明性を高め、ベンダーとの信頼関係を築く基盤としても有用です。
⑥社内での理解や合意を得やすい
メリットの6つめに、RFPを作成することで社内での理解や合意が得やすくなる点が挙げられます。
RFPは外部ベンダーへの提案依頼書であると同時に、社内の目的や要望、課題を明確に文章化する役割も果たします。作成の過程で関係部署や経営層と認識を合わせやすくなり、RFPを共有して意見交換や修正を重ねることで、合意形成をスムーズに進めることができるようになるでしょう。
これにより、後から「知らなかった」「聞いていない」といった社内トラブルを防ぐことができ、システム導入後の運用やサポート体制も整えやすくなるはずです。今後の働き方を見据えても、正確なRFPの作成はプロジェクト成功の大きなポイントとなるでしょう。
⑦提案を依頼されるベンダー側にも安心材料になる
提案を依頼されるベンダー側にも安心材料になることも、RFPの大きなメリットといえます。
RFPがしっかりと作成されていれば、要望や条件が具体的に整理されているため、ベンダーは無駄な確認や追加の問い合わせをせずに、効率よく提案準備を進めることができます。また、発注者のニーズや期待値が明確なほど、ベンダーも自社の強みを活かした最適な提案がしやすくなります。
反対に、依頼内容が曖昧だと、ベンダーはリスクを考慮して価格を高めに設定したり、十分な提案ができなかったりすることもあります。このように、RFPは発注者とベンダー双方にとってメリットがあるため、良好な関係を築くための重要なコミュニケーションツールとなるでしょう。
RFPを作成する2つのデメリット
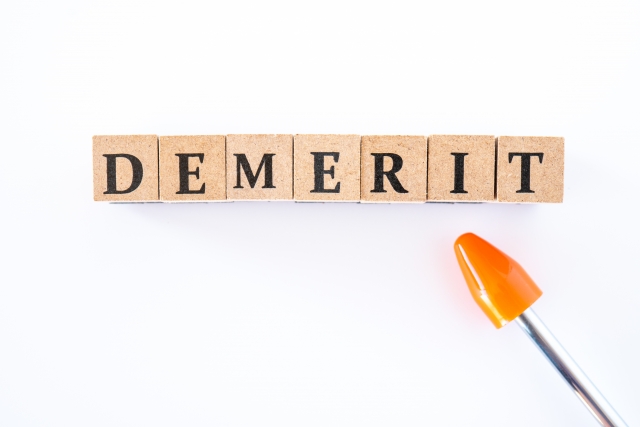
RFPを作成することには、上記でお伝えしたように、発注者側にもベンダー側にもとても多くのメリットがあります。しかし、その一方で気になるデメリットも存在します。
この章では、RFP作成に伴う代表的な2つのデメリットについて詳しく解説します。また、それぞれの特徴を理解した上で、対策方法についてもご提案するので、ぜひあわせて確認してみてください。
①RFPを作成するための時間やコストが必要
RFPを作成するデメリットの1つめは、作成にかかる時間やコストが大きいことです。
社内の関係者から情報を集め、課題や要望を整理し、文章としてまとめ上げる作業は決して簡単ではありません。場合によっては数週間から数ヶ月かかることもあり、複数の部署へのヒアリングや専門知識を持つ担当者の協力も必要となります。
さらに、外部のコンサルタントに依頼した場合、追加のコストも発生します。特にリソースの限られた中小企業にとっては大きな負担となるでしょう。
しかし、この段階を丁寧に進めることで、後の開発での品質向上やトラブル防止につながり、長期的には大きなメリットをもたらします。負担を軽減するためには、必要に応じて外部の専門家を活用したり、事前に社内の情報共有体制を整えておくことが大事です。
②システム開発までの工数がかかる
デメリットの2つめは、RFPを作成することでシステム開発までの工数が増える点です。
RFPの作成には、関係部署からのヒアリングや要件整理、ベンダーからの提案内容の評価、さらには質問や調整など、さまざまな工程が必要となります。特に複数のベンダーに提案を依頼する場合は、比較検討や面談、交渉の時間も加わり、プロジェクト全体の立ち上げまでに想定以上の時間がかかることもあります。また、RFPの内容が不十分だと後から追加要件が発生し、さらに工数が増加するリスクもあります。
この課題を解決するためには、RFP作成段階で必要な情報をできるだけ網羅し、関係者との丁寧なコミュニケーションを重ねることが重要です。初期段階でしっかり準備することで、結果的に開発工程の手戻りやトラブルを減らし、全体の効率化につなげることができます。
RFP作成と提出後の流れ

ここまで、RFPについて、その特徴やメリット・デメリットを解説しました。ここからは、実際にどのようにRFPを作成していくのかということについてご説明していきます。
RPF作成のイメージを掴むためには、全体の流れを俯瞰的に見ることが大事です。そこで、「RPFを作成する時」や「RFPを作成した後」に分けた流れとそれぞれの段階で気をつけるポイントを簡単に解説します。参考にしてみてください。
RFP作成の流れ
RFP作成の流れは、まず自社がシステム導入や開発を行う目的を明確にすることから始まります。この目的がはっきりしないと、要望や課題も曖昧になり、ベンダーに正確に伝わりません。
次に、関係部署や現場担当者へのヒアリングを行い、現状の課題や希望する機能、スケジュールなどを具体的に整理します。こうして集めた情報をもとにRFPのドラフトを作成し、必要に応じて専門家やコンサルタントのチェックを受けることで、抜け漏れや誤解を防ぎます。
その後、ドラフトを社内で何度もレビューし、関係者の意見を反映させながら内容をブラッシュアップします。このプロセスが不十分だとベンダーに誤った情報が伝わり、後のトラブルにつながるため注意が必要です。
最終的にRFPが完成したら、ベンダーに提出する準備を整え、目的やスケジュール、評価基準などを社内で再度共有し、合意を得ることが大切です。
RFPを提出した後の流れ
RFPをベンダーに提出した後は、各社から提案書が届きます。ここからは、提案内容や価格、技術力などを比較検討し、自社に最適なベンダーを選ぶプロセスに進みます。
ベンダーを比較する際には、あらかじめ決めておいた評価基準や評価項目が大きな助けになります。例えば、システムの機能やコスト、実績、信頼性、サポート体制などを項目ごとに点数化し、客観的かつ公正に評価することで、社内の合意形成もスムーズに進められます。
また、提案内容に不明点があれば、ベンダーに質問して確認し、双方の認識をすり合わせることも大切です。こうしたやり取りを経て、最終的に選定したベンダーと詳細な条件交渉や契約を行い、プロジェクトが正式にスタートします。
評価基準を明確にし、丁寧に比較・選定を進めることが、開発リスクの軽減やスムーズなプロジェクト運営のカギとなるでしょう。
RFP作成に必要な項目
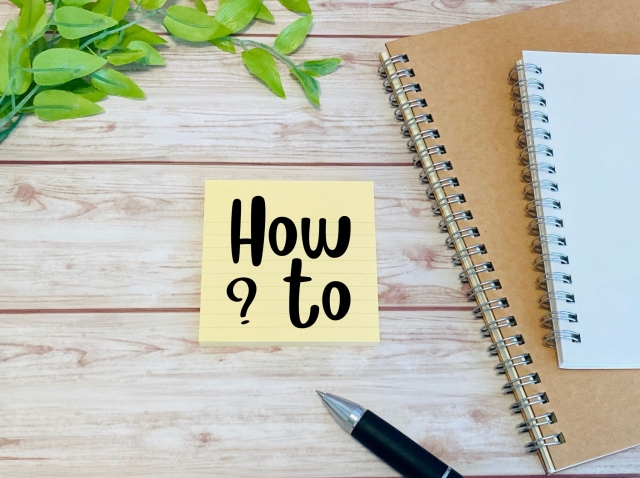
RPFは、具体的に自社のニーズを書く必要がありますが、ここで疑問になるのが、「どのように書けばベンダーに上手く伝える書類を作成できるのか」ということです。
実は、RPFには必要な項目があり、ベンダーから適切な提案を引き出すためにはこれらをしっかり網羅することが重要となります。この章では、RFPに主要な項目を順番に解説していきますので、ぜひ実践して正確にニーズが伝わるRPFを作成してみてください。
概要
RFPの「概要」は、プロジェクトの全体像をベンダーに伝えるための重要なパートで、発注者とベンダー双方の認識を揃えるための第一歩となるため、分かりやすく正確に書くことが大切です。
ここでは、導入したいシステムの目的や背景、企業の事業内容などを簡潔にまとめます。「なぜこのシステムが必要なのか」「どのような課題を解決したいのか」といった点を明確に記載することは、ベンダーがプロジェクトの方向性を正しく理解するためにとても重要になります。
また、プロジェクトのスケジュールや予算の目安もこの段階で提示しておくと、ベンダー側もより具体的な提案を検討しやすくなるでしょう。
提案依頼内容
RFPを作成する際に最も重要なのが「提案依頼内容」です。
ここでは、実現したい機能や要件、現状の課題、システム化の範囲などをできるだけ具体的に記載します。どの業務をシステム化したいのか、必須となる機能や求めるパフォーマンス、利用ユーザー数や利用環境、対応が必要な法令や規制なども明確に伝えることが重要です。
この部分が曖昧だと、ベンダーからの提案内容が不十分になり、後々のトラブルや追加対応の原因となることがあります。RFPの提案依頼内容は、ベンダーに自社の期待や要望を正確に伝えるための土台となるため、十分に検討し、抜け漏れのないようにまとめましょう。
選考の進め方
RFPには、提案を受けてからベンダーを選定するまでの進め方を明記しておくことが非常に重要です。例えば、選考スケジュールや評価基準、面談やデモの予定などをあらかじめ記載しておくことで、ベンダー側も自社の準備やスケジュール調整がしやすくなります。また、提案内容に関する質問や追加説明の方法、回答期限なども具体的に示しておくと、やり取りがスムーズになり、双方の認識違いを防ぐことができます。
このように選考プロセスを透明にしておけば、公正な競争が促進されて最適なベンダー選定につながるでしょう。RFPに選考の進め方をしっかり盛り込むことは、プロジェクト成功のための大切なポイントです。
RFP作成を成功させる9つのポイント

ここまで、RFPについてや作成方法についてお伝えしてきました。上記のように、RPFを作成する際には必要な項目を埋めていく必要があります。しかし、この項目について、ただ形式的に書くのでは上手くベンダーに伝わらない可能性があります。
そこで最後に、実際にRFPを作成する際に役立つ9つのポイントを詳しく解説します。ぜひプロジェクトをスムーズに進めるヒントにしてください。
①システム導入の目的を明確にする
まず最初に、システムを導入する目的を具体的かつ明確にすることが重要です。「業務効率を上げたい」「コスト削減をしたい」「顧客満足度を向上させたい」など、何のためにシステムを導入するのかをはっきりさせましょう。
目的が曖昧だと、ベンダーからの提案も的外れになりやすく、結果的に期待通りのシステムができない可能性があります。また、目的が明確だと社内の関係者間での認識共有もスムーズになり、合意形成がしやすくなるでしょう。
②社内の幅広い層から意見をもらう
RFPは一部の担当者だけで作成するのではなく、社内の幅広い層から意見を集めることが大切です。現場のユーザー、管理部門、経営層など、それぞれ異なる視点やニーズがあるため、これらを反映させられれば実用性の高いRFPを作成することができるでしょう。
多様な意見を取り入れることは、想定外の課題やリスクを事前に洗い出すことにもつながります。より完成度の高いRFPにするためにも、ぜひ取り組んでみてください。
③徐々にブラッシュアップしていくことを意識する
RFPは一度で完璧なものを作るのは難しく、初稿を作成した後は何度も社内で見直しや修正を重ねていくことが大切です。このプロセスを通じて、曖昧だった部分を明確にし、より実現可能な内容へと近づけていくことができます。
また、作業を進める中で新たな課題や要望が出てくることも珍しくありません。その都度、柔軟に対応できる体制を整えておくことで、最終的に完成度の高いRFPを作成することが可能です。
手間はかかりますが、この積み重ねが将来の経営やプロジェクトの成功に大きく貢献するはずですので、ぜひ粘り強く取り組んでみてください。
④実現したい要件をすべて記載する
RFPには実現したい要件を漏れなく、できるだけ詳細に記載しましょう。小さな要望でも記載しておくことで、ベンダーがそれを踏まえた提案をしやすくなります。
反対に、後から要件を追加したり変更したりすると、プロジェクト全体に影響を与えかねません。最初にしっかりと要件をまとめることが、トラブル防止にもつながります。
⑤実現可能性があり費用対効果に見合う要求をする
システム導入にあたっては、理想を追い求めすぎてしまうケースもあります。しかし、要件が高度すぎたり費用が膨らみすぎたりすると、実現が難しくなる可能性があります。
RFPでは、実現可能性を考慮しつつ、費用対効果のバランスが取れた要求を心がけてください。ベンダーからの現実的な提案を得るためにも、無理のない範囲での要望設定が重要です。
⑥RFPを提出した後の追加要求はしない
RFPをベンダーに提出した後は、基本的に追加の要求や大きな変更を避けるべきです。追加要求が頻発すると、ベンダーの対応が遅れたり、コスト増加につながったりする可能性があります。
どうしても変更が必要な場合は、影響範囲や費用、スケジュールの調整を十分に行うことが大切です。このルールを守ることで、プロジェクトの進行がスムーズになり、双方の信頼関係も保てます。
⑦RFPの作成と同時に評価基準を作成する
RFPの作成時には、提案内容を評価するための基準も同時に用意しましょう。評価基準が明確であれば、公正で客観的なベンダー選定が可能になり、社内の合意形成も円滑に進みます。
具体的には、機能性、コスト、技術力、サポート体制、納期などの観点から点数を付けて比較する方法が一般的です。評価基準が曖昧だと、選定後のトラブルや不満につながることもあるため注意が必要です。
⑧ベンダーの選定スケジュールや予算をはっきり記載する
RFPには、ベンダー選定のスケジュールや予算の上限をはっきり記載してください。これにより、ベンダーは自社のリソースや提案内容を調整しやすくなります。
スケジュールが曖昧だとプロジェクト全体の計画が立てづらくなり、無理な納期設定でトラブルが起こる可能性もあります。予算についてもオープンにすることで、実現可能な提案が集まりやすくなるでしょう。
⑨RFP作成やベンダー選定の際は専門家に相談する
RFP作成やベンダー選定は専門知識が求められるため、必要に応じて専門家に相談することも重要です。
システム開発の経験豊富なコンサルタントや外部の専門機関の助言を得ることで、質の高いRFPが作れ、適切なベンダー選びが可能になります。また、専門家はトラブル防止や契約面の注意点もアドバイスしてくれるため、安心してプロジェクトを進められるでしょう。
RFP作成や要件定義でお困りの方は株式会社KIYOLACAへ

RFPはシステム導入や開発を成功させるための重要なツールです。正しく作成することで、自社の要望を明確にベンダーに伝えられ、最適な提案を受けることが可能になります。
今回解説したように、RFPと要件定義書の違いやRFI、RFQとの違いを理解し、メリットやデメリット、成功のポイントを押さえることが大切です。しかし、初めての作成や複雑な案件では難しさを感じるかもしれません。
そのような時におすすめなのが、株式会社KIYOLACAです。KIYOLACAには、大手SI企業や外資系企業での実務経験を持つコンサルタントが多数在籍しており、ハイレベルな専門知識と現場経験を活かしたコンサルティングが可能です。RFP作成やベンダー選定などのプロジェクトの立ち上げから運用まで一貫してサポートしています。
自社に合ったシステム導入の成功率を上げたい企業様、迅速にシステムを導入されたい企業様は特に、専門家からの視点を利用されてみてはいかがでしょうか。